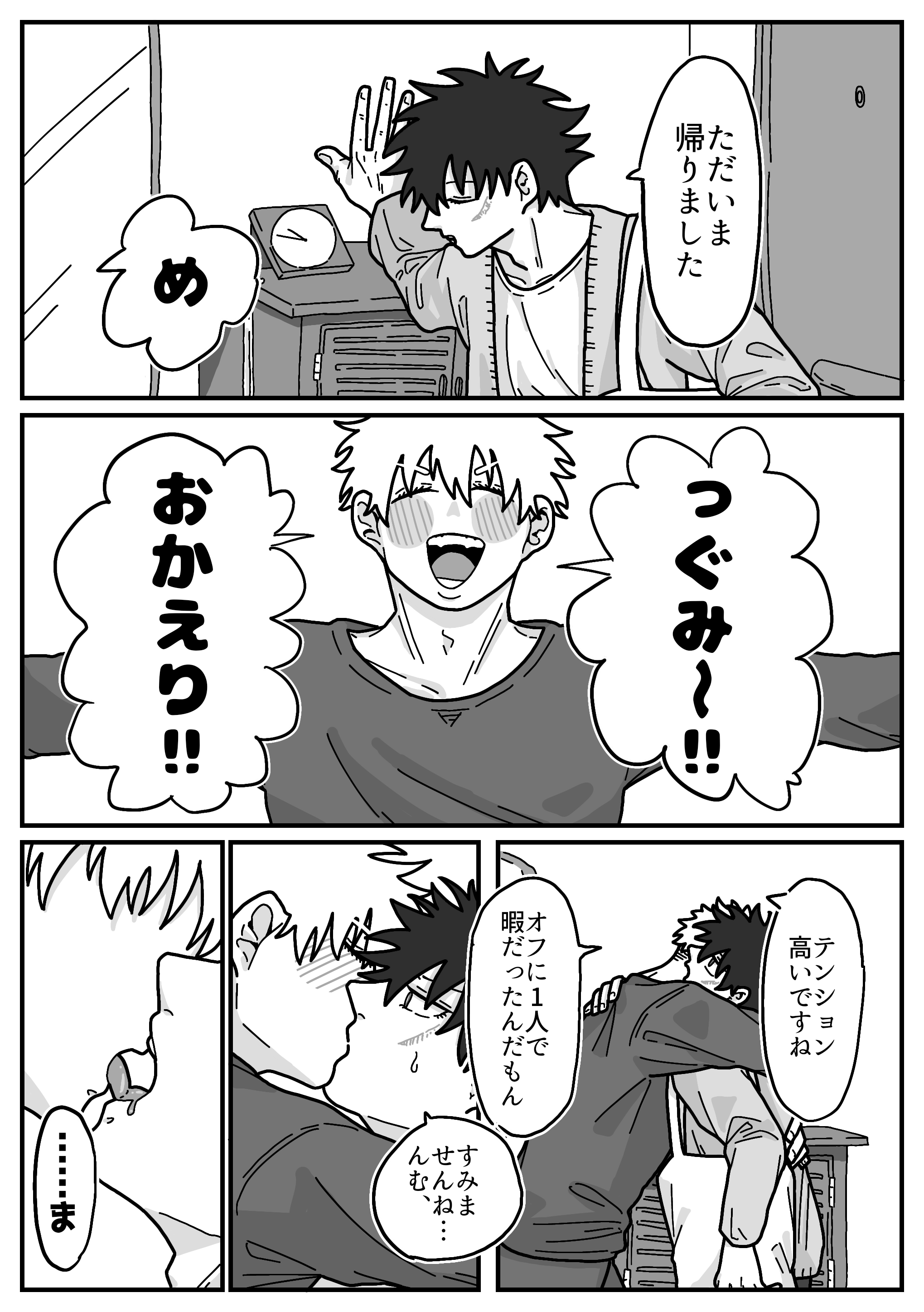薄明
ごじょうさとる×ふしぐろめぐみ
非公式二次創作ブログサイト
メイン
2025年9月の投稿[11件]
2025年9月25日 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する
2025年9月24日 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する
匂わせ
「あれ?」
任務に向かう道でふと立ち止まった虎杖が不思議そうに首を傾げる。なんだ?と言いながら伏黒の周りをぐるりと1周歩いて、もう一度首を捻った。
「…おい、」
早く向かうぞ、と言いかけたところでぱちんと虎杖が指を鳴らした。
「シャンプー変えた!?」
違和感の答えを見つけ、ぱっと顔を明るくした虎杖には一つも悪気はない。ただただ風に乗って流れてきた香りがいつもと違うからなんだろうと不思議に思っただけ。なのだけど。
「…………」
実際昨夜の伏黒はいつもと違うシャンプーを使ったし、なんならコンディショナーも使った。使ったというか、使わされたというか。ドラッグストアでセールになっていたよく分からないメーカーの安いシャンプーじゃなくて、よく分からないメーカーのボトルから高級感の漂う香りもすごくいい高そうなシャンプーとコンディショナー。つまるところ有り体にざっくり言ってしまえば、昨夜は五条の部屋に泊まりに行っていて、一緒に風呂に入らされた。一応抵抗はしたのだが、五条相手に抵抗なんて意味はない。
「伏黒?」
「……いや、まあ、そんなのはどうでもいいだろ」
「そ?めっちゃ怖い顔してるけど」
「元々こんな顔だ」
にしてもめっちゃ良い匂いすんね、と言う虎杖を置いて足早に任務先に向かう。きっと、こうして歩いている間にも風に乗って高級シャンプーの香りは伏黒から漂っているのだろう。爽やかで、でも少し甘い、五条が好きそうで伏黒が嫌がらなそうな香りが。
___
「…なんか匂うな」
「いい香りでしょ」
窓から吹き込む風に乗って五条から漂ってきた香りに、家入が少し眉根を寄せる。任務先で怪我をしたという釘崎の様子を見に保健室へやってきたのだが、ベッド脇に腰掛けて治療を受けていた釘崎も家入と同じような顔をした。
「…なにこれ、あま」
「そ、甘いけど爽やかでいいでしょ」
家入も釘崎も「いいでしょ」という言葉に同意は示さずに、お互いと視線を合わせる。女の勘ってやつかもしれない。
「…お前、こんなの普段使ってないだろ」
「まぁね。香り強いの好きじゃないし」
「匂わせする男は嫌われるわよ」
ふわふわと髪から漂うのは、少し前に買ったお高いシャンプーの香り。どこのメーカーのかは知らないけれど、香りと持続時間だけで選んだそれは中々悪くない。買ったのは少し前だけど、使ったのは昨夜が初めて。何故なら、このシャンプーは伏黒の為に買ったからだ。
昨夜、伏黒が五条の部屋に泊まりにきた。ただ何をするでもなくゆっくり過ごしていたけれど、このシャンプーの存在を思い出して渋い顔をする伏黒を風呂場に連れて行った。変に身構える伏黒をむっつりだとからかいながらくせっ毛を洗ってあげて、ケアもしてあげて、2人で湯船に浸かって、おしまい。伏黒が身構えてたようなことは何一つしないまま2人で布団にもぐりこんで、お揃いのいい香りで眠りについたのだ。
「匂わせじゃなくて、お揃いって言ってよ。微笑ましいでしょ」
「匂いでやるとか趣味悪〜」
釘崎が風に乗ってくる香りを振り払うように顔の前で手を振る。何も言わないけれど、たぶん家入も同じ感想だ。
2人でゆっくり過ごせたのは随分と久しぶりで、言葉にしないだけで伏黒も浮かれていたようだったから玄関先で別れる時も同じ香りを纏っていることを気にした様子はなかった。けれど今日は虎杖と任務だと言っていたし、朝から向かっていた筈だから何事もなければそろそろ戻ってくる時間。流石にもう意味に気付いているだろう。怒るかな、1番に照れ隠しのパンチが飛んでくるかも。どれがきても可愛いことには変わりがないので、釘崎の無事を改めて確認してから保健室を出た。お揃いの香りを纏う伏黒を出迎えてあげるのだ。
畳む
「あれ?」
任務に向かう道でふと立ち止まった虎杖が不思議そうに首を傾げる。なんだ?と言いながら伏黒の周りをぐるりと1周歩いて、もう一度首を捻った。
「…おい、」
早く向かうぞ、と言いかけたところでぱちんと虎杖が指を鳴らした。
「シャンプー変えた!?」
違和感の答えを見つけ、ぱっと顔を明るくした虎杖には一つも悪気はない。ただただ風に乗って流れてきた香りがいつもと違うからなんだろうと不思議に思っただけ。なのだけど。
「…………」
実際昨夜の伏黒はいつもと違うシャンプーを使ったし、なんならコンディショナーも使った。使ったというか、使わされたというか。ドラッグストアでセールになっていたよく分からないメーカーの安いシャンプーじゃなくて、よく分からないメーカーのボトルから高級感の漂う香りもすごくいい高そうなシャンプーとコンディショナー。つまるところ有り体にざっくり言ってしまえば、昨夜は五条の部屋に泊まりに行っていて、一緒に風呂に入らされた。一応抵抗はしたのだが、五条相手に抵抗なんて意味はない。
「伏黒?」
「……いや、まあ、そんなのはどうでもいいだろ」
「そ?めっちゃ怖い顔してるけど」
「元々こんな顔だ」
にしてもめっちゃ良い匂いすんね、と言う虎杖を置いて足早に任務先に向かう。きっと、こうして歩いている間にも風に乗って高級シャンプーの香りは伏黒から漂っているのだろう。爽やかで、でも少し甘い、五条が好きそうで伏黒が嫌がらなそうな香りが。
___
「…なんか匂うな」
「いい香りでしょ」
窓から吹き込む風に乗って五条から漂ってきた香りに、家入が少し眉根を寄せる。任務先で怪我をしたという釘崎の様子を見に保健室へやってきたのだが、ベッド脇に腰掛けて治療を受けていた釘崎も家入と同じような顔をした。
「…なにこれ、あま」
「そ、甘いけど爽やかでいいでしょ」
家入も釘崎も「いいでしょ」という言葉に同意は示さずに、お互いと視線を合わせる。女の勘ってやつかもしれない。
「…お前、こんなの普段使ってないだろ」
「まぁね。香り強いの好きじゃないし」
「匂わせする男は嫌われるわよ」
ふわふわと髪から漂うのは、少し前に買ったお高いシャンプーの香り。どこのメーカーのかは知らないけれど、香りと持続時間だけで選んだそれは中々悪くない。買ったのは少し前だけど、使ったのは昨夜が初めて。何故なら、このシャンプーは伏黒の為に買ったからだ。
昨夜、伏黒が五条の部屋に泊まりにきた。ただ何をするでもなくゆっくり過ごしていたけれど、このシャンプーの存在を思い出して渋い顔をする伏黒を風呂場に連れて行った。変に身構える伏黒をむっつりだとからかいながらくせっ毛を洗ってあげて、ケアもしてあげて、2人で湯船に浸かって、おしまい。伏黒が身構えてたようなことは何一つしないまま2人で布団にもぐりこんで、お揃いのいい香りで眠りについたのだ。
「匂わせじゃなくて、お揃いって言ってよ。微笑ましいでしょ」
「匂いでやるとか趣味悪〜」
釘崎が風に乗ってくる香りを振り払うように顔の前で手を振る。何も言わないけれど、たぶん家入も同じ感想だ。
2人でゆっくり過ごせたのは随分と久しぶりで、言葉にしないだけで伏黒も浮かれていたようだったから玄関先で別れる時も同じ香りを纏っていることを気にした様子はなかった。けれど今日は虎杖と任務だと言っていたし、朝から向かっていた筈だから何事もなければそろそろ戻ってくる時間。流石にもう意味に気付いているだろう。怒るかな、1番に照れ隠しのパンチが飛んでくるかも。どれがきても可愛いことには変わりがないので、釘崎の無事を改めて確認してから保健室を出た。お揃いの香りを纏う伏黒を出迎えてあげるのだ。
畳む
2025年9月20日 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する
2025年9月16日 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する
2025年9月14日 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する
内緒の話
その日は9月の半ばにしてはやけに暑い日だった。
津美紀と暮らしていたオンボロの安アパートじゃクーラーなんてものはなくて、学校から帰って一番にすることと言ったら窓を開け放して扇風機を回すこと。その日、津美紀は委員会で少し帰りが遅く、俺が先に帰っていつ壊れてもおかしくない扇風機を回して籠った熱気が薄まるのを待っていた。蝉の鳴き声はもうしない、静かで暑い日。
「あれ、津美紀は?」
「…ノック」
「それ言うならちゃんと鍵閉めな」
インターホンなんてものもなかったあのアパートで来客を知らせるものといったらノックしかなかったが、五条さんはいつも無断で入ってくる。合鍵を持っているから俺が鍵を閉めたって意味なんてないのだけど、帰宅して一番に鍵を閉めなかったのは自分なので黙った。
「んで、津美紀どうしたの?」
「委員会。少し帰り遅くなるって」
「へぇ、子供でも仕事なんて大変だねぇ」
「ていうか、何しにきたんですか」
「息抜き。疲れたの」
言うなり人の家の床に寝そべった五条さんは「津美紀帰ってきたら起こして」と言い残してサングラスを外した。それをちゃぶ台の上に適当に放り投げて、目を閉じて寝る体勢に入るもんだから邪魔だとどかそうとしたけれど小さかった俺じゃ大きな五条さんの身体はびくともしなかった。たまに意味もなく俺たちの暮らす家にやってきては、稽古や任務に連れて行くでもなくただ構い倒して帰っていく。数時間もしないで帰る時もあれば1泊していく時もあって、多分幼い頃の俺と津美紀にとってこの頃の五条さんは凄い人だとかそんなイメージはあまりなかった。
この日も例に漏れず意味もなくやってきた五条さんは本当に疲れていたようで、広くもないアパートの一室で遠慮なく足を伸ばして寝始めた。布団もクッションも何も無い、ただの畳の上で寝こける五条さんに、俺は内心緊張していた。
少し前に五条さんが半年くらい家に来なかった時期があった。お金だけは五条さんと一緒に仕事をしているという疲れた顔をした男の人が持ってきてくれたけれど、姿はとんと見えなくなって連絡も途絶えた。お金を持ってきてくれる人に聞いてみても仕事が立て込んでいるとしか教えてくれなくて、最初は本当に忙しいんだなと納得していたけれど半年も経つ頃にはまた捨てられたのだと気持ちに整理をつけ始めていた。が、急に人の家にやってきた五条さんは本当に忙しすぎて顔を見せれなかっただけらしく、海外に行ってただとか寝る暇もなかっただとか半年分の苦労を語るだけ語った末に俺にこう言った。
「ごめんって、捨てたりしないからむくれないでよ」
この出来事が、たぶん、俺の恋の気付きというやつだ。捨てられたのが悲しくて、本当は一緒にいたくて、会えたのが嬉しくて、そういう気持ちはきっと恋の中にある。そんな気付きから少しして津美紀が少女漫画にハマって、自分がドキドキしたシーンなんかを見せてくるから余計に俺の中では恋というものの存在が大きくなっていた。この頃はたぶんまだ恋はきらきらしたものだと漫画から刷り込まれていた。それから恋なんて捨てたくなるようになるのは別の話だし、その捨てたい恋が報われるのも一先ず別の話だ。
そんなわけで恋に気付いてしまった俺は、目の前で寝こける五条さんにどきどきしていた。津美紀が読んでいた漫画で見たキスというものが頭をよぎって、それが好き合っている人間同士がするものだとは分かっていても好奇心と初めての恋に浮かれる気持ちとは無敵なもので。
「………寝てる」
ちょん、と五条さんの頬をつついてみても綺麗に閉じられた瞼はぴくりとも動かない。思い切って揺すってみても起きる気配はなくて、扇風機の音すら聞こえないほど心臓がうるさく鳴り始める。
五条さんの顔の横で小さく身体を丸めて、全身の血がお湯になったんじゃないかってくらい熱くて、ゆっくり近づいて、ちょん、と触れた唇は柔らかかった。
時間にして1秒に満たないくらい。慌てて離れたけれど、五条さんはそのまま起きる気配はなかった。実は起きてたらどうしようだとか、どこかでバレたらどうしようだとか、色んなことが頭をよぎって、その日の晩御飯は味がしなかった。
「…ねぇ、ちゅーすんなら起きてる時にしてよ」
「起きてたんですか」
眉間に皺を寄せて瞼を持ち上げた五条さんはむくれたように口を尖らせた。どうやらずっと起きていたらしい。布団の中でもぞもぞと動いて向き直った五条さんが、俺の頬に手を寄せる。今度は起きてる状態の五条さんにしろということか。
「この間も寝てる僕にしてたでしょ」
「しましたね」
「起きてる時にしてよ」
「…善処します」
善処じゃなくってさぁ!と騒ぎそうな口にちょんと自分の唇を触れさせて黙らせる。この間もなにも、実は寝てる五条さんに遭遇する度に毎回しているのだが、バレるかバレないかは半々というところだ。6日前にソファで寝落ちていた五条さんにしたのはバレていないらしい。
趣味、というわけではないが寝てる五条さんにキスをするのは密かな楽しみというか、初心に戻れるというか、なんにせよ気に入っているのだ。普段はうるさかったりいじわるだったりいやらしかったりする五条さんの唇は、寝てる間はただ柔らかいだけ。その柔らかさに昔みたいにどきどきするのは、五条さんにはずっと内緒の別の話だ。
畳む
その日は9月の半ばにしてはやけに暑い日だった。
津美紀と暮らしていたオンボロの安アパートじゃクーラーなんてものはなくて、学校から帰って一番にすることと言ったら窓を開け放して扇風機を回すこと。その日、津美紀は委員会で少し帰りが遅く、俺が先に帰っていつ壊れてもおかしくない扇風機を回して籠った熱気が薄まるのを待っていた。蝉の鳴き声はもうしない、静かで暑い日。
「あれ、津美紀は?」
「…ノック」
「それ言うならちゃんと鍵閉めな」
インターホンなんてものもなかったあのアパートで来客を知らせるものといったらノックしかなかったが、五条さんはいつも無断で入ってくる。合鍵を持っているから俺が鍵を閉めたって意味なんてないのだけど、帰宅して一番に鍵を閉めなかったのは自分なので黙った。
「んで、津美紀どうしたの?」
「委員会。少し帰り遅くなるって」
「へぇ、子供でも仕事なんて大変だねぇ」
「ていうか、何しにきたんですか」
「息抜き。疲れたの」
言うなり人の家の床に寝そべった五条さんは「津美紀帰ってきたら起こして」と言い残してサングラスを外した。それをちゃぶ台の上に適当に放り投げて、目を閉じて寝る体勢に入るもんだから邪魔だとどかそうとしたけれど小さかった俺じゃ大きな五条さんの身体はびくともしなかった。たまに意味もなく俺たちの暮らす家にやってきては、稽古や任務に連れて行くでもなくただ構い倒して帰っていく。数時間もしないで帰る時もあれば1泊していく時もあって、多分幼い頃の俺と津美紀にとってこの頃の五条さんは凄い人だとかそんなイメージはあまりなかった。
この日も例に漏れず意味もなくやってきた五条さんは本当に疲れていたようで、広くもないアパートの一室で遠慮なく足を伸ばして寝始めた。布団もクッションも何も無い、ただの畳の上で寝こける五条さんに、俺は内心緊張していた。
少し前に五条さんが半年くらい家に来なかった時期があった。お金だけは五条さんと一緒に仕事をしているという疲れた顔をした男の人が持ってきてくれたけれど、姿はとんと見えなくなって連絡も途絶えた。お金を持ってきてくれる人に聞いてみても仕事が立て込んでいるとしか教えてくれなくて、最初は本当に忙しいんだなと納得していたけれど半年も経つ頃にはまた捨てられたのだと気持ちに整理をつけ始めていた。が、急に人の家にやってきた五条さんは本当に忙しすぎて顔を見せれなかっただけらしく、海外に行ってただとか寝る暇もなかっただとか半年分の苦労を語るだけ語った末に俺にこう言った。
「ごめんって、捨てたりしないからむくれないでよ」
この出来事が、たぶん、俺の恋の気付きというやつだ。捨てられたのが悲しくて、本当は一緒にいたくて、会えたのが嬉しくて、そういう気持ちはきっと恋の中にある。そんな気付きから少しして津美紀が少女漫画にハマって、自分がドキドキしたシーンなんかを見せてくるから余計に俺の中では恋というものの存在が大きくなっていた。この頃はたぶんまだ恋はきらきらしたものだと漫画から刷り込まれていた。それから恋なんて捨てたくなるようになるのは別の話だし、その捨てたい恋が報われるのも一先ず別の話だ。
そんなわけで恋に気付いてしまった俺は、目の前で寝こける五条さんにどきどきしていた。津美紀が読んでいた漫画で見たキスというものが頭をよぎって、それが好き合っている人間同士がするものだとは分かっていても好奇心と初めての恋に浮かれる気持ちとは無敵なもので。
「………寝てる」
ちょん、と五条さんの頬をつついてみても綺麗に閉じられた瞼はぴくりとも動かない。思い切って揺すってみても起きる気配はなくて、扇風機の音すら聞こえないほど心臓がうるさく鳴り始める。
五条さんの顔の横で小さく身体を丸めて、全身の血がお湯になったんじゃないかってくらい熱くて、ゆっくり近づいて、ちょん、と触れた唇は柔らかかった。
時間にして1秒に満たないくらい。慌てて離れたけれど、五条さんはそのまま起きる気配はなかった。実は起きてたらどうしようだとか、どこかでバレたらどうしようだとか、色んなことが頭をよぎって、その日の晩御飯は味がしなかった。
「…ねぇ、ちゅーすんなら起きてる時にしてよ」
「起きてたんですか」
眉間に皺を寄せて瞼を持ち上げた五条さんはむくれたように口を尖らせた。どうやらずっと起きていたらしい。布団の中でもぞもぞと動いて向き直った五条さんが、俺の頬に手を寄せる。今度は起きてる状態の五条さんにしろということか。
「この間も寝てる僕にしてたでしょ」
「しましたね」
「起きてる時にしてよ」
「…善処します」
善処じゃなくってさぁ!と騒ぎそうな口にちょんと自分の唇を触れさせて黙らせる。この間もなにも、実は寝てる五条さんに遭遇する度に毎回しているのだが、バレるかバレないかは半々というところだ。6日前にソファで寝落ちていた五条さんにしたのはバレていないらしい。
趣味、というわけではないが寝てる五条さんにキスをするのは密かな楽しみというか、初心に戻れるというか、なんにせよ気に入っているのだ。普段はうるさかったりいじわるだったりいやらしかったりする五条さんの唇は、寝てる間はただ柔らかいだけ。その柔らかさに昔みたいにどきどきするのは、五条さんにはずっと内緒の別の話だ。
畳む
2025年9月13日 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する
2025年9月10日 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する
小説より奇なり
子供が小さくて弱くて脆い生き物だというのは分かっていた。けれどそれは知識として理解しているだけで、実体験としては理解していなかった。
子供の平均的な体型なんて知らないけれど、それでもまともな食事が取れていない故の細っこい身体。骨と皮だけ、とまでは言わないけれどちょっと強く掴んだら簡単に折れちゃいそうなくらい脆く見えた。実際その脆さは思っていた通りで、連れて行った任務で恵の腕をぽっきり折ってしまった時に硝子にこっぴどく叱られながら意識を改めたものだった。子供って手がかかって(今思えば恵も津美紀も子供にしては聞き分けが良すぎて手なんてまるでかからなかったのだけど)気を遣う。めんどくさいな、なんて思ったりもしていた。それでも誰かに恵のことを任せたくなかったのは、知らぬ間に僕の中で恵の存在がその辺の適当な人たちとは違う場所に居たからだ。平たく言っちゃえば大事になってたってこと。
「…鼻歌ウザイんすけど」
「子供の成長を喜んでんのよ」
「はぁ…」
そんな細くて貧弱で簡単に死んじゃいそうな子供は、今はすくすくと育って体重も増え、僕にはボコボコにされるけど簡単には死なないようになり、ついでにちょっとふてぶてしくなった。ノリのいい鼻歌に文句を言いながらも、僕が恵の手を離さないのには文句言わないんだよね。昔は恵の手なんて本当に小さくて、片手で両方掴めるとかじゃなくて片手で両方握り潰せそうなくらい小さな豆粒サイズだった。それが今やしっかり繋ぎ返して指まで絡めてくるサイズ感だ。
「そういえば明日」
「ん?」
「……スーツとか、ちゃんとした格好した方がいいですかね、やっぱ」
子供の成長は早いなんて言うけれど、実のところ変わったのは見た目だけじゃなくて関係も。出会った頃はまさか指を絡めて手を繋ぐような仲になるなんて思ってもみなかったし、恵のお姉さんに僕たちの関係を報告する日がくるとも思ってなかった。
明日、僕と恵は津美紀に「実は付き合ってます」の報告をしに行く。今日はその前乗りで、2人揃って任務をお休みして津美紀の家の近くに宿を取ったのだ。そしてその宿に向かう道中ってわけ。お互い多忙で、直前まで仕事だったから宿に向かうのも月が顔を出す時間になってしまった。
恵が高専を卒業すると同時に2人で暮らし始めるのかと思いきや、津美紀にNOを突きつけられて恵と津美紀は別々に暮らしている。なんとなく、その時点で津美紀は何かを察している気がするけれど、恵には黙っている。びっくりしすぎて固まる恵は見たいしね。
「別にいつも通りでいいんじゃないの?そこまでかしこまるような場じゃないし。てか、お互い任務から直で来てんだからスーツなんて持ってきてないじゃん」
「…そこはほら、五条さんが買ってくれるんじゃないかと」
「現地調達で?」
そうです、と当然の顔をして頷くもんだから「お前ってさぁ!」と笑って思わずおでこを小突く。スーツくらい欲しいんならいくらでも買ってあげるけれど、当然みたいな顔しちゃって。といってもそうやって育てたのは他でもない僕だけど。
「でもほんと、スーツとかいらないよ。そのまんまの僕たちでいつも通りに過ごしてさ、付き合ってますって言おうよ。いつからってのは…まぁ、ぼかそう」
「叱られますからね」
小さく笑って恵が僕と繋いだままの手をゆらゆらと揺らした。
あんなに小さかった手が、今じゃ絶対離したくない大事な手になってるんだから人生ってのは小説より奇なりってやつだ。
畳む
子供が小さくて弱くて脆い生き物だというのは分かっていた。けれどそれは知識として理解しているだけで、実体験としては理解していなかった。
子供の平均的な体型なんて知らないけれど、それでもまともな食事が取れていない故の細っこい身体。骨と皮だけ、とまでは言わないけれどちょっと強く掴んだら簡単に折れちゃいそうなくらい脆く見えた。実際その脆さは思っていた通りで、連れて行った任務で恵の腕をぽっきり折ってしまった時に硝子にこっぴどく叱られながら意識を改めたものだった。子供って手がかかって(今思えば恵も津美紀も子供にしては聞き分けが良すぎて手なんてまるでかからなかったのだけど)気を遣う。めんどくさいな、なんて思ったりもしていた。それでも誰かに恵のことを任せたくなかったのは、知らぬ間に僕の中で恵の存在がその辺の適当な人たちとは違う場所に居たからだ。平たく言っちゃえば大事になってたってこと。
「…鼻歌ウザイんすけど」
「子供の成長を喜んでんのよ」
「はぁ…」
そんな細くて貧弱で簡単に死んじゃいそうな子供は、今はすくすくと育って体重も増え、僕にはボコボコにされるけど簡単には死なないようになり、ついでにちょっとふてぶてしくなった。ノリのいい鼻歌に文句を言いながらも、僕が恵の手を離さないのには文句言わないんだよね。昔は恵の手なんて本当に小さくて、片手で両方掴めるとかじゃなくて片手で両方握り潰せそうなくらい小さな豆粒サイズだった。それが今やしっかり繋ぎ返して指まで絡めてくるサイズ感だ。
「そういえば明日」
「ん?」
「……スーツとか、ちゃんとした格好した方がいいですかね、やっぱ」
子供の成長は早いなんて言うけれど、実のところ変わったのは見た目だけじゃなくて関係も。出会った頃はまさか指を絡めて手を繋ぐような仲になるなんて思ってもみなかったし、恵のお姉さんに僕たちの関係を報告する日がくるとも思ってなかった。
明日、僕と恵は津美紀に「実は付き合ってます」の報告をしに行く。今日はその前乗りで、2人揃って任務をお休みして津美紀の家の近くに宿を取ったのだ。そしてその宿に向かう道中ってわけ。お互い多忙で、直前まで仕事だったから宿に向かうのも月が顔を出す時間になってしまった。
恵が高専を卒業すると同時に2人で暮らし始めるのかと思いきや、津美紀にNOを突きつけられて恵と津美紀は別々に暮らしている。なんとなく、その時点で津美紀は何かを察している気がするけれど、恵には黙っている。びっくりしすぎて固まる恵は見たいしね。
「別にいつも通りでいいんじゃないの?そこまでかしこまるような場じゃないし。てか、お互い任務から直で来てんだからスーツなんて持ってきてないじゃん」
「…そこはほら、五条さんが買ってくれるんじゃないかと」
「現地調達で?」
そうです、と当然の顔をして頷くもんだから「お前ってさぁ!」と笑って思わずおでこを小突く。スーツくらい欲しいんならいくらでも買ってあげるけれど、当然みたいな顔しちゃって。といってもそうやって育てたのは他でもない僕だけど。
「でもほんと、スーツとかいらないよ。そのまんまの僕たちでいつも通りに過ごしてさ、付き合ってますって言おうよ。いつからってのは…まぁ、ぼかそう」
「叱られますからね」
小さく笑って恵が僕と繋いだままの手をゆらゆらと揺らした。
あんなに小さかった手が、今じゃ絶対離したくない大事な手になってるんだから人生ってのは小説より奇なりってやつだ。
畳む
2025年9月9日 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する
2025年9月7日 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する
2025年9月2日 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する
Powered by てがろぐ Ver 4.2.0.